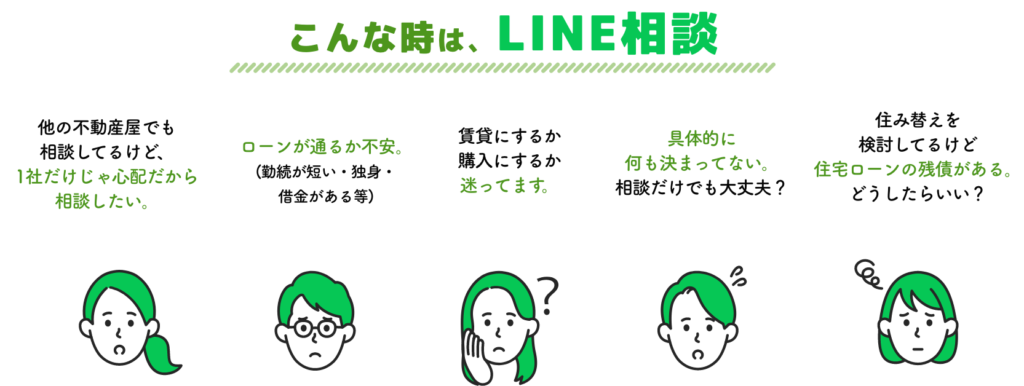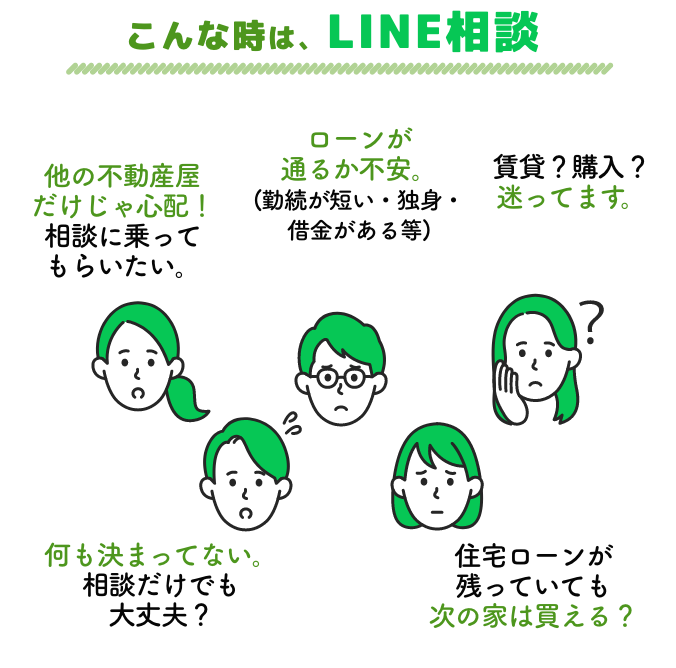(★4.8/5)
夫婦でずっと悩んでいた名義の問題がスッキリ解決!この記事に出会えて本当に良かった
(30代女性・会社員)
「”夫の名義にするのが普通?”そんなふうに思っていませんか?
でも実は、後悔した夫婦もたくさんいます。 知らないうちに年間数十万円も損をしていたり、家族関係がギクシャクしてしまったり…。
家を買うことを決めた共働き夫婦の8割以上が、住宅ローンの名義について迷いを感じています。安心してください。この悩み、あなただけではありません。
でも大丈夫。今日は住宅ローンの名義について、あなたたち夫婦が納得できる選び方をわかりやすく解説します。無理に急いで決める必要はありません。 しっかり理解してから、安心して進みましょう。
住宅ローンの名義、どう決める?|共働き夫婦のよくある悩み

「夫婦どちらにすべきか決めきれない…」という声が多い理由
「なんで名義でこんなに悩むの?」 そう思うかもしれませんが、実はとても自然なことです。
- 収入の違い: 夫の方が多い?妻の方が安定している?
- 将来の不安: 育休や転職で収入が変わったらどうなる?
- 税金の優遇: 住宅ローン控除を最大限活用したい
- 夫婦の関係性: 平等に責任を負いたい?それとも分担したい?
これらすべてを一度に考えるのは、プロでも大変なことです。 あなたが悩むのは当然ですし、焦って決める必要はありません。
「名義=責任と権利」将来に影響する選択
住宅ローンの名義は、単なる手続きではありません。以下のような重要な意味があります:
✅ 返済責任: 誰がどれだけ返済する義務があるか
✅ 所有権: 家の持分(権利)をどう分けるか
✅ 税制優遇: 住宅ローン控除や贈与税の扱い
✅ 将来のリスク: 離婚や相続時の取り扱い
「よく分からないから、とりあえず夫名義で」は危険です。 後で変更するのは非常に困難なので、今しっかり理解しておきましょう。
実際に名義で揉めた夫婦のリアル事例
Dさん夫婦(30代・共働き)の場合:
「夫名義で住宅ローンを組んだのですが、私も半分返済しているのに『俺の家だから』と言われてショックでした。最初にちゃんと話し合っておけば良かった…」
Eさん夫婦(40代・共働き)の場合:
「え、ローン控除って夫婦で受けられるの!?って知ったのは、住宅ローンを組んだ直後。知人に『2人の名義にしとけばもっと戻ってきたのに』って言われて青ざめました。毎年10万、13年で130万…完全に見落としてた…!」
このような後悔をしないために、今から一緒に学んでいきましょう。
名義の基本|3つの住宅ローンの組み方と、それぞれの特徴

住宅ローンの組み方には、大きく分けて3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解して、あなたたち夫婦に合った方法を見つけましょう。
【1】単独名義ローンとは?メリット・デメリット
単独名義ローン = 夫婦のどちらか一方の名義でローンを組む方法
- 手続きが簡単(1人分の書類だけでOK)
- 団体信用生命保険で名義人に万一のことがあればローン完済
- 意思決定が早い(売却時などの判断が1人で可能)
- 借入限度額が低い(1人の年収ベース)
- 住宅ローン控除が1人分しか使えない
- 家の持分について夫婦間でトラブルになりやすい(2人で支払っている場合)
- 一方の収入が圧倒的に多い
- シンプルな管理を望む
- 借入額がそれほど大きくない
【2】連帯債務ローンとは?メリット・デメリット
連帯債務ローン = 夫婦2人で1本の住宅ローンを組み、両方が主な返済義務を負うローンの形
- 借入限度額が大きくなる(2人の年収を合算)
- 住宅ローン控除を2人とも受けられる
- 家の持分が明確になる
- 団体信用生命保険も2人とも加入(金融機関によっては片方のみ加入も可能)
- どちらかが払えなくなると、もう一方が全額返済義務を負う(失業・病気・離婚等)
- 将来の持分変更やローン借り換えが難しくなる
- 住宅ローン控除を使いきれない場合は損(どちらかがパートや失業になった場合等)
- 2人とも安定した収入がある
- 借入額が大きい
- 税制優遇を最大限活用したい
【3】連帯債務・連帯保証とは?違いと注意点
連帯債務
夫婦が共同でローンの返済義務を負い、お互いに不動産の持分を持つ
- 住宅ローン控除:債務者双方が対象(収入に応じて)
- 団体信用生命保険:持分割合に応じて(金融機関による)
- 責任:どちらも債務者 → 全額返済義務あり
連帯保証
夫婦が共同でローンの返済義務を負うが、保証人は不動産の持分は持たない
- 住宅ローン控除:主債務者のみ
- 団体信用生命保険:主債務者のみ
- 責任:主債務者が払えないときに代わりに返済義務あり
名義で後悔しないために|収入・将来設計・税金のリアルな視点

💰 重要:名義によって、控除額に100万円以上の差が出ることもあります。
【税金】住宅ローン控除を最大限に活かすには?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を所得税・住民税から控除できる制度です。
🔍 知っておきたい控除の仕組み ※2025年時点
- 控除期間: 新築なら13年間、中古は10年間
- 年間控除限度額: 最大315,000円(物件により異なる)
- 所得税から優先控除 → 引ききれない分は住民税(上限97,500円)から控除
💡 2人で控除を受ける方が得なケース
夫年収500万円・妻年収250万円の夫婦で4,500万円借りた場合(最大控除額315,000円):
| パターン | 夫の控除額 | 妻の控除額 | 合計控除額 |
| 夫単独名義 | 約25万円 | 0円 | 約25万円 |
| 連帯債務 | 約25万円 | 約14万円 | 31.5万円 |
年間6.5万円、13年間で約80万円の差!
ただし、妻の所得税・住民税が少ない場合は効果が限定的です。
【ライフプラン】育休・転職・キャリア計画をふまえた名義の選び方
出産や転職で収入が変わっても大丈夫な名義選択が重要です。
出産・育休を考慮した選択
- 育休前年収:400万円
- 育休中年収:150万円(育児給付金)
- 住宅ローン控除への影響: 控除額が大幅減少
- 育休予定者の借入割合を少なめにする
- 復職後の収入回復を見込んで判断
- 無理のない返済計画を最優先に
転職・キャリアチェンジリスク
- 夫: 安定企業勤務、収入アップ見込み
- 妻: 専門職、転職や独立の可能性
- 安定性を重視するなら主収入者中心
- 柔軟性を重視するなら分散投資的な考え方
【リスク】離婚や相続時にトラブルにならないためのチェックポイント
「もしものとき」も考えておくことで、家族を守れます。
離婚時のリスクと対策
- 家の持分と返済負担の不一致
- ローンが残っているのに片方が家を出る
- 売却したいのに同意が得られない
- 持分と返済負担を一致させる
- 売却条件を事前に話し合う
- 公正証書での取り決めも検討
相続時の注意点
- 相続時に配偶者が住み続けられない可能性
- 相続税の負担
- 相続人が増えて権利関係が複雑化
- 売却時の同意取得が困難
「もしものとき」を考えるのは辛いかもしれませんが、愛する家族のために準備しておくことが大切です。
実例で学ぶ|名義の選び方で差が出た夫婦たち

Case 1:”納得して話し合えた”Aさん夫妻のケース
夫(35歳・会社員・年収600万円)の声:
「最初は僕の名義だけで考えていたんです」
妻(32歳・看護師・年収450万円)の声:
「でも私の仕事の方が安定してるし、控除も2人で受けたいなって」
最終的な選択: 連帯債務(夫6:妻4の割合)
結果:
「控除額が年間30万円近くになったのが大きかったですね。2人で話し合って決めたので、どちらも納得しています」
- 妻の職業(看護師)の安定性を評価
- 住宅ローン控除を2人で活用
- 将来子どもを考えても無理のない返済計画
Case 2:”なんとなく流されて決めた”Bさんの後悔とは
夫(38歳・営業・年収600万円)の声:
「銀行の人に『ご主人名義が一般的ですよ』と言われて…」
妻(36歳・事務・年収300万円)の声:
「深く考えずに夫名義にしてしまいました」
- 5年後にボーナスが減少。妻の住宅ローン控除を活用できず年間約10万円の損失
- 妻が家に対する愛着を持ちにくい
- 家事・育児の分担で「俺の家だから」という発言が出てしまった
現在:
「住宅ローンの借り換えのタイミングで、連帯債務への変更を検討中です。最初にもっと勉強しておけば良かったと本当に後悔しています」
Case 3:”保証人ってどういうこと?”で揉めそうになったCさんの事例
夫(29歳・公務員・年収400万円)の声:
「銀行から『奥様に連帯保証人になってもらえば』と提案されて」
妻(28歳・会社員・年収350万円)の声:
「保証人って何?責任だけあって権利がないってこと?」
- 連帯保証人 = 夫が返済困難になったら妻が全額返済義務
- 住宅ローン控除は夫のみ
- 家の持分も夫のみ(贈与税のリスクあり)
✅ 最終的な選択: ペアローン(夫5:妻5)
「お互いが対等なパートナーとして家を持てているという実感があります」
💡 事例から学ぶポイント
✅ 夫婦でしっかり話し合っている
✅ メリット・デメリットを理解している
✅ 将来のライフプランを考慮している
✅ 「なんとなく」ではなく「納得」で決めている
あなたも納得の選択をしませんか? → LINE無料相談で専門家と話してみる
よくある質問まとめ|共働き家庭の住宅ローン名義Q&A

Q1. ローン返済は折半なのに、名義は片方だけでいい?
A. 税務上のリスクがあるため、おすすめできません。
リスクの具体例:
- 夫名義なのに妻が返済 → 贈与税の対象になる可能性
- 年間110万円を超える負担は贈与とみなされる場合がある
解決策:
- 返済負担割合と持分を一致させる
- 連帯債務やペアローンで正式に責任分担する
Q2. 妻がパートでも名義人になれる?
A. パートでも安定した収入があれば名義人になれます。
目安としては:
- 年収150万円以上
- 勤続年数1年以上
- 正社員の配偶者がいる場合は条件が緩和されることも
注意点: パート収入での借入限度額は低いため、主たる借入者は正社員の配偶者にすることが一般的です。
Q3. 住宅ローン控除は2人分受けられるの?
A. 名義の組み方によります。
| 名義パターン | 控除を受けられる人 |
| 単独名義 | 名義人のみ |
| ペアローン | 夫婦両方 |
| 連帯債務 | 夫婦両方(持分に応じて) |
| 連帯保証 | 主債務者のみ |
重要: 控除を受けるには、その人に所得税・住民税の納税義務があることが前提です。
Q4. フラット35ではどの名義が有利?
A. フラット35の特徴を活かすなら、以下がポイントです。
✅ 夫婦でしっかり話し合っている
✅ メリット・デメリットを理解している
✅ 将来のライフプランを考慮している
✅ 「なんとなく」ではなく「納得」で決めている
- 固定金利で安心
- 夫婦合算で借入額を増やせる
- 連帯債務が利用しやすい
- 夫婦合算(連帯債務) → 借入額アップ+2人で控除
- 収入合算者の年収が主債務者の年収の2分の1以上なら特にメリット大
Q5. あとから名義変更はできる?
A. 可能ではありますが、手続きが困難で費用も高額です。
名義変更に必要なこと:
- 新しい名義人での審査通過
- 登記費用・税金(数十万円〜)
- 金融機関の承諾、手数料・保証料等
だからこそ最初の選択が重要です。 迷ったら専門家に相談しましょう。
【迷ったら】中立な専門家に相談を|名義は”住宅選びの起点”になる

金融機関は「借りられる視点」、私たちは「暮らしと未来の視点」
銀行や不動産会社は、「いくら借りられるか」「手続きの簡単さ」 を中心に提案してきます。でも、あなたたち夫婦にとって本当に大切なのは:
✅ 無理のない返済計画
✅ 夫婦が納得できる責任分担
✅ 将来のライフプランとの整合性
✅ 税制優遇の最大活用
「借りられる」と「借りるべき」は違います。 あなたたちの幸せな暮らしを最優先に考えましょう。
ご夫婦で納得して決めるための”売らない相談”という選択肢
こんなふうに感じていませんか?
✅ 「うちはどのパターンが一番お得なんだろう?」
✅ 「なんとなく夫名義で進んでるけど、本当に大丈夫かな?」
✅ 「夫婦で意見が分かれて、どう決めればいいか分からない」
「なんとなく」や「言われるがまま」で決めてしまって、後で後悔する夫婦をたくさん見てきました。
私たちは、住宅ローンの名義について以下のスタンスで相談をお受けしています:
✅ 特定の金融機関を推奨しません
✅ 夫婦の価値観を最優先にします
✅ メリット・デメリットを包み隠さずお伝えします
✅ 将来のリスクも含めて検討します
大切なのは、あなたたち夫婦が「これで良かった」と思える選択をすることです。
まとめ|住宅ローンの名義は夫婦の未来への投資

あなたたちのペースで、納得いくまで検討しましょう
住宅ローンの名義選択は、確かに複雑で悩ましい問題です。でも、急いで決める必要はありません。
- 夫婦でしっかり話し合うこと
- メリット・デメリットを理解すること
- 将来のライフプランを考慮すること
- 納得できる選択をすること
「正解」は夫婦によって違います。 他の人の選択に惑わされず、あなたたちらしい答えを見つけてください。
一生に一度の大きな決断だからこそ、サポートを活用してください
私たちは「家を売る」専門家ではなく、「夫婦の幸せな暮らし」を応援する専門家です。
住宅ローンの名義で悩んでいる方、将来への不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたたち夫婦が心から納得できる選択をサポートします。
「あの時、相談して良かった」 そう思っていただけるよう、全力でサポートいたします。